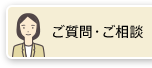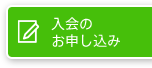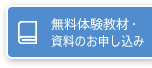「学力検査」の問題
理科…「両方あっていて正解」の問題がなくなっていて、それぞれに配点があった。
数学は、前半の問題で時間を使いすぎないように気を付けた。得意な問題を落とさないことが大切。 時間が余ったら必ず見直しをしよう。問題を解くなかでマークをつけると後で見返したときにわかりやすくて良いと思うよ。
特色検査
共通問題で得点の土台を作った。選択問題の方は、落ち着いて問題を読んで、学校で習った知識と関連させたり、消去法を使ったりしたよ。
「学力検査」の問題
国語は、問3までは順調だったのに古文が予想外の理解のしづらさで得点源のはずが15分かけて一問しか当たらなかった。数学も少し形式が変わったことで得点源の空間図形問題が減っていたので難しかった。
少し時間をかけてみてきつそうだった問題は、躊躇わずに飛ばしまくった。難しいのは時間をかけても仕方がないのでできるだけ簡単なものから解いて、余った時間を見直しや難問に使うと効率よく点数稼ぎが出来ると思った。
特色検査
問1、2は実施校共通で、私の高校は問5,6を選択して解いた。印象に残ったのは、問1の英文の問題に計算問題が二問出題されて時間がとられたこと。しかも計算ミスを誘ってくるような問題だった。問6は思ったよりも難しくなく、文章の要点を素早く見つけて理解して解く問題だった。
問1、問2は他の大問に比べてクセがなく、一問の配点が高いのでそこでできる限りの点数稼ぎをすることが合否を分けると思った。それでも大問ひとつ当たり15分を目安に配分していくと効率よく解けた。そもそも満点をとるテストではないので、時間がかかる問題は飛ばした方が点数がとれた。
「学力検査」の問題
5教科とも、形式が少しだけ違ったことが予想外だった。
入試までにたくさんの問題を解いておいたので、似たような問題もいくつかあった。自分を信じていたので、自信を持って問題を解くことができた。
「学力検査」の問題
英語の長文で意訳がついてるけど難しめな単語が出てきて、内容を読み取るのが大変だった。数学で、得意だった角度の問題だったり分かりそうで分からない問題が多かった。
解いてみて分からない問題は、練習で決めておいた時間を過ぎたら一旦飛ばして、解ける問題を確実に終わらせてから戻ると焦らずできた!
特色検査
QRコードについての英文や、「内輪差」の計算みたいな問題があった。
特色検査は「分からなくてもしょうがない」精神で解いていった。