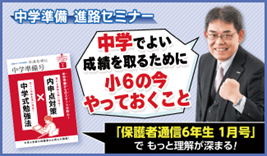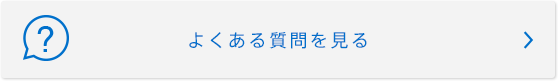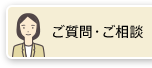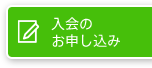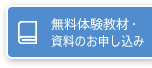ニガテを常に意識 “わからない”をなくして、受験のスタートダッシュへ!
小6|2月号りお先輩 2024年度入試で合格
トクイ教科:数学 ニガテ教科:英語
部活:卓球部
志望校合格までの壁:コツコツ勉強はしていたものの、受験勉強のボリュームに圧倒され、効率のいい勉強法を探すことに腐心した。
▼ 体験談から読む
▼「小6の2月号おすすめ活用法」を先に読む
中学準備
長期休みの間に、
小学校までのニガテをつぶしきる!
小学校の頃は正直勉強が嫌いで、「ゼミ」がたまってしまうこともしばしば。学校の宿題をこなすのが精一杯のときもありました。
ただ、冬休みや春休みのように、時間が取れる期間はコツコツ勉強をがんばりました。特に力を入れたのは、ニガテの克服。いつまでに「ゼミ」を終わらせようと目標を立てて、毎日机に向かいました。解いた「ゼミ」の問題は、全部の問題が◯になるまで、何度も解き直しました。
今だからこそわかるのですが、中学の英語や数学は積み重ねがとても大切で、一つ基礎がわからなくなるとどんどんわからなくなっていきます。小学校のときにニガテをなくしておいたことはもちろん、ニガテ克服に向き合う姿勢を身につけておいたのは、大げさでなく志望校合格に結びついたと思います。
内申点対策
わからないことがあったら
すぐに解消し、ニガテをつくらない
中学校に上がってからはとにかく部活が忙しくて、なかなかまとまった勉強時間が取れなくなっていたので、日常の中でニガテを克服することを意識していました。具体的には、部活が終わったあとに顧問の先生に授業の内容を質問する、成績が優秀な友だちにわからないことを聞く、などです。
放っておくと、ニガテはどんどん広がっていくもの。だからこそ、わからないことがあったらすぐに人に聞いて、“わからない”がない状態で過ごすようにしていました。
志望校選び
カッコいい姉の姿を見て、
憧れた小学生時代
私には歳の離れた姉がいて、私が小学校のときに高知小津高校に通っていました。あるとき、姉が文化祭で書道パフォーマンスを行うと聞いて、家族で見に行くことに。大きな筆で迫力ある書を行う姉の姿はとてもカッコよく、同じく書道をしていた私は「この高校で、姉のように筆を取りたい!」とすっかり憧れていました。
中学に上がってからも気持ちは変わらず、高知小津高校が第一志望校。中学で実際に部活動を経験してからは、高知小津高校の文武両道の校風に、さらにひかれるようになりました。

受験勉強
問題演習の仕方をブラッシュアップ
私が通っていた中学校は「自主学習ノート」と言って、何でもいいので自主学習に取り組んで提出するノートがありました。中3に上がって、このノートに「ゼミ」の問題を解くようになったのが、私の受験勉強のスタートでした。
ノートに書くのは解答だけではありません。ノートの余白がなくなるくらいまで、「ゼミ」の解説を丁寧に写し、問題への理解をどんどん深めていきました。また、問題を解くときは必ず時間も計るように。どんな問題に、どのくらい時間がかかるのかを把握したことで、模試や入試本番の時間配分で困ることはありませんでした。
範囲が広いからこそ、
効率よく暗記に取り組む
受験期に入ってすぐに力を入れた勉強がもう一つあります。それは、英単語や社会・理科の用語の暗記です。受験勉強の範囲はボリュームがあります。私はもともと手で書いて覚えるのが好きだったのですが、すべての教科・単元の単語や用語を書いていては終わらないので、勉強法を変えることに。
〈入試によく出る基礎〉の単語や用語を赤シートで隠し、口頭で言えるかで、覚えているかをチェック。言えなかった単語や用語だけ、ノートに書き取り、効率よく暗記を進めました。
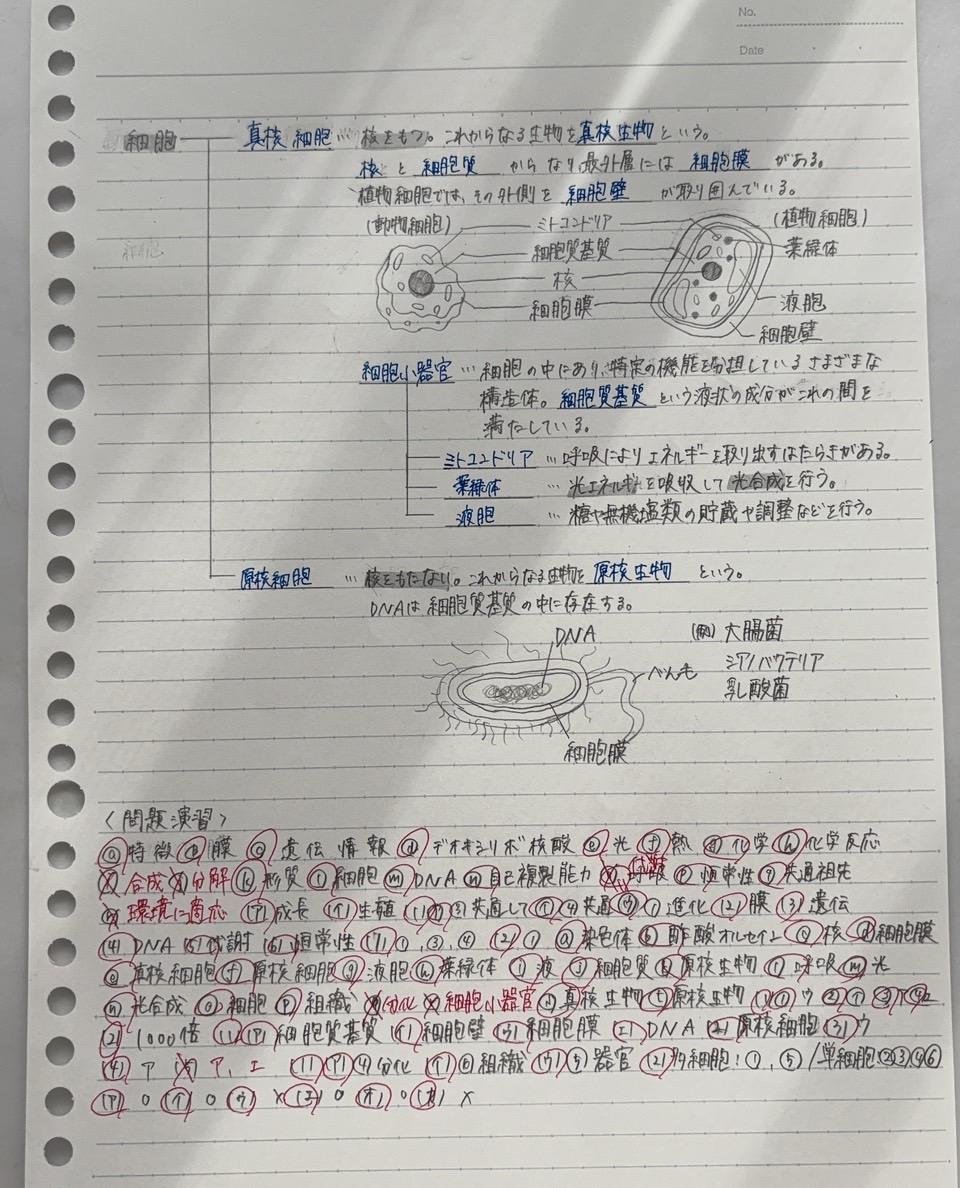
入試本番
数学で思わず涙
それでも必死に解答欄を埋める
「落ちたかもしれない…」。受験当日、数学の試験が終わったときは、本気でそう思いました。予想よりずっと問題が難しくて、解けた手ごたえがなかったからです。試験が終わってすぐ、泣きそうになりながらお手洗いへ。「とにかく次の教科だ」と、顔を洗って無理やり気持ちを切り替えました。
残りの教科は2つだったのですが、どちらも解答中は空欄をつくらないように必死。なんとかやり切った気分で、試験を終えました。しばらくハラハラしていましたが、合格できて本当によかったです。
合格の秘訣
早めに勉強をスタートして、
自分に合った勉強法を見つけたこと
中学、高校と、その場その場で私は勉強法を変えてきました。例えば、高校に入ってから私は朝学習を始め、朝のちょっとしたスキマ時間を勉強に費やしています。
自分にとって一番効率がいい勉強法を見つけるには、時間がかかります。だからこそ、早めにコツコツ勉強する習慣をつけておいてよかったと思いますね。みなさんも、中1から少しでも勉強に取り組んで、受験までに自分が思う最高の勉強法を見つけてください。
(お母様から)上からではなく、
同じ目線で勉強に向き合う
小学校の頃は、娘も言っていたように、比較的「ゼミ」をためてしまう子だったかもしれません。それでも、口うるさく「やりなさい」と言ってはいませんでした。
どちらかというと、取り組むための計画立てや、取り組んだあとのご褒美を“一緒に”考えることに腐心していましたね。無理に勉強させたくないようなら、“一緒に”計画を立てる、“一緒に”勉強するくらいの距離感で接するのも一つの手だと思います。
※体験談は2024年度の入試情報です。
「進研ゼミ」で志望校合格へ!
小6の2月号おすすめ活用法
早めに解消が成功のカギ! ニガテ対策
中学につながる単元を、
集中的にニガテ解消!
小学校での学びは、中学からの学習の土台となります。これまでの学びの総まとめを効率よく行い、中学校での勉強に備えましょう。
2月号の『中学準備講座』では、6年生のニガテになりやすい単元を集中対策。小学校最後の「まとめテスト」でもよい点数をめざせます。
「ニガテ意識が芽生えたら早めに解消する」「広い学習範囲を復習する」という習慣を身につけておくと、中学入学後の定期テスト対策にも役立ちます。
中学校の成績の上げ方は?
セミナー録画公開中!
「通知表は、小学校とどう違うの?」「テストに向けて、今からできる勉強法は?」などの疑問に、まるっとお答え。12月26日(木)に開催した、中学準備進路セミナーの録画を公開中です。
高校受験の内申点にも影響する中学校の成績。小学校との違いや、成績の上げ方をお子さまにもわかりやすく解説しました。
「進研ゼミ」の先輩からのアドバイスや、中学入学前の今こそやっておきたい学習の準備などもお伝えしています。ぜひご家族でご視聴ください。
▼参加された方の声
「普段知ることのできない高校入試対策や、内申点のしくみを詳しくご説明いただいたのでとても理解しやすかったです」(保護者の方)
「親子で見られる内容なのがよいですし、このような受験に向けた授業は受験へ対する意識も高まります」(保護者の方)
「親から注意しても聞いていないところがあったので、同じことでも第三者にお話ししてもらえたのは助かりました。子どもも気が引き締まったようです」(保護者の方)
「中学校での大切なことや、小学校のうちにやっておいたほうがよいことなどがわかったので、今からやっていきたいと思いました。セミナーわかりやすかったです」(お子さま)
「中学校の勉強は難しそうだけれど、おもしろいところもいっぱいありそうなので、頑張っていこうと思った」(お子さま)